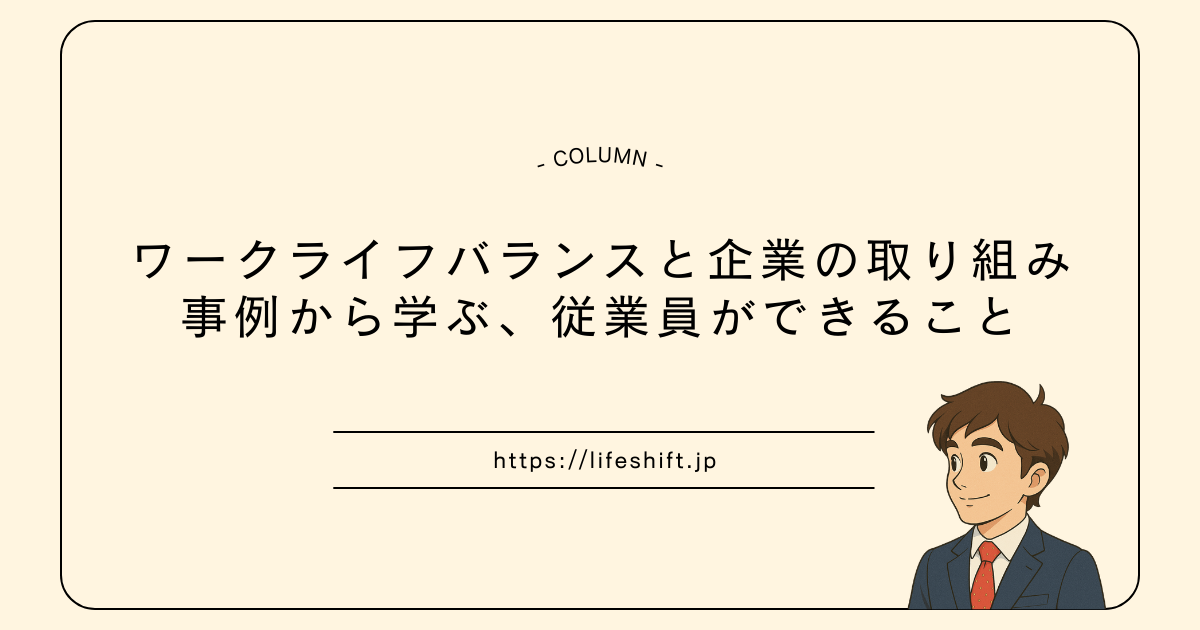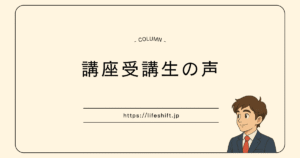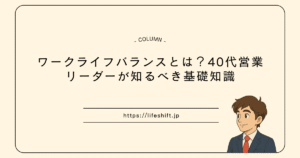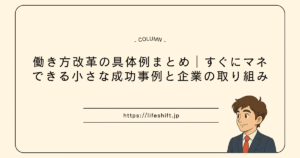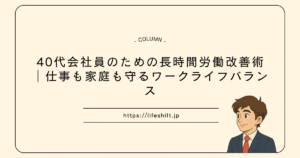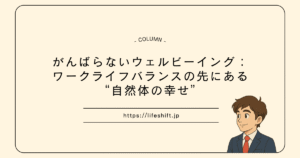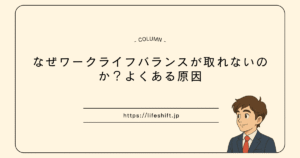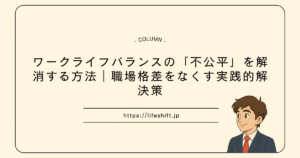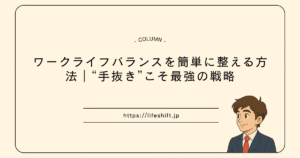企業が進めるワークライフバランスの取り組みとは?
「ワークライフバランス(WLB)」という言葉は、すっかり社会に定着しました。
企業の採用ページでも「働きやすい環境づくり」「プライベートも大切に」といった言葉を見かけることが増えていますし、国も推進しています。調べてみると、内閣府は「社内におけるワーク・ライフ・バランス浸透・定着に向けたポイント・好事例集」という資料を示していて、経営トップから現場の管理職まで、それぞれの立場で何をすべきかをまとめていました。施策を要約すると代表的なポイントは以下の通りと思います。
- 経営トップが本気を示す:制度を作るだけでなく「経営戦略」として位置づける。
- 管理職が率先して取り組む:部下にだけ残業削減を求めるのではなく、自分自身が休暇を取り、定時で帰る姿勢を見せる。
- 業務効率化を徹底する:会議の削減、マニュアル化、ITツールの導入など。
- 進捗を「見える化」する:残業時間や有給取得状況を共有し、改善の進み具合を示す。
- 従業員が「自分ごと」として取り組む環境を整える:社内表彰や情報共有を通じて主体性を促す。
また、多くの企業の取り組み事例も紹介がありましたので、以下簡単に。
- フレックスタイム制・裁量労働制の導入
- テレワーク・在宅勤務の普及
- ノー残業デーや有給休暇取得奨励
- 社内での健康経営プログラムやメンタルサポート制度
こうした施策には共通して、経営戦略の一部として「人材を大事にしたい」という企業の想いがあります。採用力を強化し、優秀な人材の離職を防ぐこと。それらによって「従業員の満足度を高め、組織全体の力を伸ばしたい」という想いです。経営戦略を描き、また推進するのも結局は人材です。優れた人材の確保は常に経営の主要な戦略であり続けます。
それでもワークライフバランスが進まないのはなぜか?
ワークライフバランスに関する制度や仕組みは整いつつあるのに、「実際にはなかなか変わらない」と感じる人も少なくはないのでは思います。内閣府資料を見ながら、その理由を色々考えてみて大きく以下の3つに集約しました。
経営層・管理職のリーダーシップ不足
トップが「ワークライフバランスを大切に」と発信しても、中間管理職が長時間労働を続けていたらどうでしょう?
現場は「結局は口だけ」と受け取ってしまうと思います。また、経営層から中間管理職に対して予算達成のプレッシャーだけ与えていてはやはり中間管理職もワークライフバランスというより仕事に集中せざるを得ません。組織の一部でもワークライフバランスを軽視するような組織文化では徐々に全体がもとに戻っていくと思います。ワークライフバランスの観点だけの掛け声のみでは現場の行動は変わらないと思います。
従業員の心理的抵抗
「周りが残っているのに自分だけ帰っていいのか」
「休暇を取ったら評価が下がるのでは」
こうした同調圧力や不安が、制度を使いにくくしているように思います。日本企業特有の「真面目で責任感が強い」文化が裏目に出ているとも言えそうです。勝手に従業員が思い込んでいるという可能性と、各職場を司る中間管理職の考えがなかなか改まらないという両方の側面があると思います。
業務量と人員のアンバランス
もう一つ、忘れてはいけない大きな壁としては「物理的な制約」もあると思っています。
業績が厳しいから人を増やせない → 一人あたりの業務量が増える → 長時間労働が常態化する → 改善の余裕すらなくなる。
こうした悪循環に陥っている職場も少なくないのではと想像しています。
また、一部の職場のワークライフバランスが改善した場合、その裏側で対面となる部局の業務が増加している可能性もあります。業務全体のサプライチェーンを見通して、業務の合理化・スリム化を進めるといった施策が必要でしょうね。
体験談から
ここで少し、私自身の体験も少しお話ししたいと思います。
会社の営業部門の中間管理職だった時代です。海外案件の担当をしていたときは、当然ですが出張や時差をまたいだ打ち合わせが続き、日本にいても早朝や深夜に会議が入り、結構多忙な時期が続いていました。
担当案件への責任感から「仕事の成果のためには、自分が発揮できる時間とエネルギーを注ぎ込むべきだ」と思い、走り続ける日々が続いていました。
その結果どうなったか。
休息や家族との時間は後回しになり、健康を維持するのも大変であったと思います。中間管理職は時間管理の対象外となり体調管理も自己責任になるものなのですが、このあたりの自覚が不足していたということと、仕事への責任感が勝り、自分に常に負荷をかけ続けていたように思います。
いい年になっていたこともあり、段々無理も聞かなくなって、体力的に「このままでは持たない」と危機感を抱いたのです。そこから学んだのは、
- 本当に大事なところに注力し、そうでないところは力を抜くこと
- 周囲に頼ることは弱さではなく組織としての強さであり、自分もある場面では助ける側になること
- ついては、助け助けられる良好な人間関係を構築することが重要
ということでした。
この気づきは、いまコーチとして働き方をサポートする中でも、強い実感を持ってお伝えしていることです。
従業員の立場でできること
では、制度や環境に限界がある中で、従業員として何ができるのでしょうか。
私はよく、クライアントにこう問いかけます。
「あなたが本当に望むワークライフバランスとは、どんな状態ですか? それはなぜですか?」
ワークライフバランスは、「仕事とプライベートのどちらを大切にするか」の二者択一ではありません。
むしろ「自分が何を大事にしたいのか」という価値観の現れです。
その上で、個人が実践できる工夫を5つご紹介します。
1. 業務を整理して「不要な仕事」を減らす
- タスクを重要度と緊急度で仕分ける
- 書類や資料はテンプレート化して繰り返し作業を減らす
- 「これは本当に必要か?」を問い直し、ムダを削る勇気を持つ
業務に慣れてしまった人ほど「これは本当に必要な業務なのだろうか?」と疑うのは難しいものです。担当業務が変わった時、異動直後、引き継ぎを受けている時、自分が疑問に思ったことは質問したり、書き留めておくと良いでしょう。
2. 集中時間を確保して効率を高める
- 通知をオフにして、短時間でも集中できる環境を作る
- メールやチャットはまとめて処理する
- 作業を習慣化して切り替えコストを下げる
朝から夜まで集中力を保ち続けるのは人間難しいので、意識的にリズムを作っていく必要があると思います。ランチタイム前後はゆっくりする前提で誰かとランチを楽しみ、リフレッシュして午後に臨む等多くの人がやっていると思いますが、このような観点でリフレッシュするタイミングを試行錯誤すると良いと思います。
3. 会議を見直す
- 「自分が参加しなくても良い会議」に出ない勇気
- 会議前に論点を整理してから参加し、ダラダラとした時間を減らす
- 議論が脱線したら「次回に回しましょう」と提案してみる
大きく分けて報告と議論という2つの要素があると思いますが、報告であればメール等で済ませて今後の取り組み方だけ口頭で報告してもらうとか、議論であれば可能であれば事前に論点を共有して自分の意見やスタンスを明確にできると良いと思っています。
4. 休養と健康管理を“仕事の一部”と考える
- 睡眠・運動・食事を整えることは生産性への投資
- 計画的に休暇を取り、心身をリセットする
- 健康であること自体が最大のパフォーマンス源泉
特に40代以降になると重要になってくる課題だなと思います。懇親会の翌日などは集中力も落ちたりしますので、事前に想定して仕事も組み立てられると良いですね。また、会社や自宅近くのジムで運動するなど、運動を組み込むと脳の血流が増加して頭も活性化するように思います。
5. 周囲に頼る・協力する
- チーム内で進捗や負荷を共有し、仕事を抱え込まない
- 得意領域を活かして補い合う
- 早めに「ヘルプ」を出すことが結果的にチーム全体を救う
これは特に若いうちは苦手な分野でしたが、プレイングマネージャーになってくると必要ですね。周囲をよく見て誰がどんな仕事を担当していて各々の仕事の進捗や課題は何かも把握しておく必要があると思います。
まとめ:制度を待つだけでは変わらない
企業がワークライフバランスを推進する取り組みは確かに増えています。
しかし現場では「業務量が多すぎて動けない」「周囲の目が気になって休めない」といった壁が残っています。
会社の制度充実も重要ですが、一方でそれを活用する従業員側からも働きかけが必要だと感じています。従業員自身が小さな一歩を踏み出すことが、ワークライフバランス改善のカギになると思います。
私自身も、長時間労働に追われた経験から「すべてに全力は持たない」「頼ることは弱さではなく戦略」と気づきました。
👉 私の講座では、ワークライフバランスを「自分ごと」として捉え直し、行動に移すための具体的なステップをお伝えしています。
一緒に、自分らしい働き方を描いていきませんか?