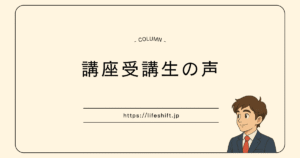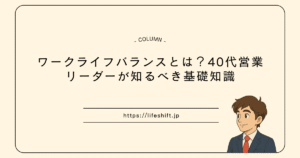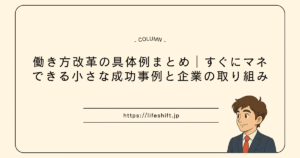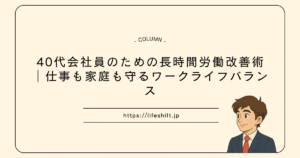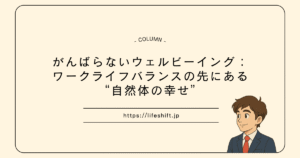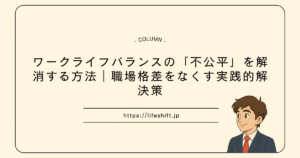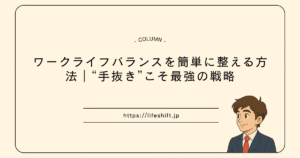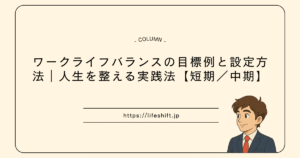なぜワークライフバランスが取れないのか?よくある原因7選

ワークライフバランスはうまく取りたいと思うんですけど、現実なかなか難しいんですよねぇ。。
ワークライフバランスをうまく取れると毎日がもっと充実すると願いつつ、なかなかうまく取るのは難しいですよね。
今日はワークライフバランスをうまく取ることが難しい原因を考察し、その改善に役立てていただきたいと思います。
難しい原因としては、大きく以下の7つが挙げられるのではと思っています。
日本特有の「長時間労働文化」と残業の常態化
非管理職も管理職もついつい残業が状態化しているケースが多いのではと思います。
アウトプットの品質を限りなく向上させようと思ったら、いくらでも時間はかけられるものです。
許された時間の中で全てを費やして限りなく品質を高めていく姿勢では、ワークライフバランスをうまく取ることは難しいでしょう。
どこかで区切りをつける必要があります。
上司や組織の「働いている姿勢」を評価する文化
評価する側もされる側もアウトプットで評価するというよりは仕事に取り組む姿勢を見せることで評価する、評価を上げるという事もよく見られます。
特に管理職は時間管理の対象外なので時間をかければ良いというものでもないのですが、アウトプットで評価することが難しい場合は勤務態度や勤務している時間でその努力を推し量ろうとするものです。
人員不足や役割過多による仕事の押し付け
仕事が増える一方で人員が不足していて、それが向上的になっている場合も見受けられます。
仕事は増えるものの難しいのは減らすことです。
重要ではない仕事は削減するという努力をしないと仕事は増える一方です。
一時的な仕事増と思って現状人員だけで頑張っているとそれが恒常的になっていき、いつも忙しいという状況になりがちです。
家庭・育児・介護との両立による多重負担
夫婦で共働きの世帯も多くなってきており、育児・介護などの事情を抱えた社員も増加しています。
長寿命化が進む一方で、労働力は貴重になる方向ですので、事情を抱えた社員でも貴重な戦力担って貰う必要がありますが、サポートする体制を整備しきれていないという事もよく見られます。
今後益々増加しそうですね。
自分のキャリアや価値観を見直す時間が取れない
目の前の仕事が増加するとその対応で必死になり、そもそも自分の仕事に対する価値観はどうなのか、就業観に照らしてどのように取り組んでいくかといった長期的な視点・取り組みを考える余裕がなくなっていきます。
緊急性の高い仕事が増えていきがちです。
成果を優先するあまり「休むこと」に罪悪感を感じる心理
仕事に対する責任感があるので、このような多忙な状況になってくると休むことへの罪悪感も増えてきます。
人間のエネルギーは無限ではありませんので、どこかでリフレッシュとかリラックスする時間も必要なのですが、いよいよそのリミットにぶつかってくる状況になっていきます。
ITの発展による「いつでも仕事ができる」状態に
コロナ禍以降はノートPCやスマホ支給が進み、特にホワイトカラーは自宅でも仕事ができる環境になってきました。
いつでも・どこでも仕事ができる環境が整備され、またメールが飛び交うようになると益々仕事のことがいつも気になってきます。
「会社で成果を出したい」と「自分の時間を大事にしたい」の本音ギャップ
仕事の成果を上げようと思うと、どうしても長い時間がかかることになります。
プライベートの時間を削ってでも責任感を持って仕事の完遂や品質を上げようと努力するわけです。
締め切りが決まっているなど一時的な仕事増であれば良いのですが、問題はそれが恒常的になってくることです。
仕事をきっちりやりきらないといけないという責任感や評価されたいという気持ちと、たまにはゆっくり休みたいという本音とがぶつかることになります。
体にムチを打って仕事を一生懸命こなすうちに、自分の本音と乖離していったり、疲れてくると自分の本音にも気づきにくくなります。
更には、働き盛りの世代の場合、増えてくる部下の育成という時間のかかる役職にもなりますし、家庭の大黒柱という側面もありますので、益々仕事中心になっていくという事情も出てきます。
また、毎年の業務目標も常にハードルが上げられます。昨年度と同じで良いと言う訳にはいきません。
毎年追加的な努力が増加していき、どこかで自分の体力やエネルギーの上限を迎えることになるでしょう。
時間は「投資資産」―自分のリソース配分を見直す
そのような状況を解決する方向性としては、自分の時間やエネルギーは有限であるという事実を見つめ直し、自分の健康管理の観点やプライベートとのバランスも考慮して、仕事に対する時間の上限を設定するということが大事だと思います。
仕事に頑張りすぎると場合によっては病気になることもありえます。
一度病気になると回復するには相応の時間がかかるものですし、場合によっては回復しないこともありえます。
自分の人生以上に大事なものはありません。そして自分の人生を支える土台は自身の健康であると考えます。
このままのペースで仕事をしていったら将来どうなるのかをシミュレーションし、体調不良・病気・燃え尽き症候群等にならないか、周囲にそういった事例は何かないかを調べてみましょう。
また、趣味や家族との時間を大切にすることで、リフレッシュしたり、新たなやる気が出てきたり、新しいアイデアが湧いたりすることもあります。
また、対人関係でも仕事だけの人間より趣味や家族を大切にしている人の方が概して魅力的です。仕事上の人間関係も改善するのではと思います。
人生は生まれてから死ぬまでの時間と捉えれば、その時間を仕事やプライベートにどう割り振るかは大事な資産をどうポートフォリオを作っていくかということになります。
仕事に取り組むことで得られるもの、プライベートに投じることで得られるもの、そのバランスをシミュレーションして、自分にとってベストな時間配分を考えることが良いのではと思います。
時間は投資資産という見方です。
ワークライフバランスを取り戻すための実践ステップ
ワークライフバランスを取り戻すためには以下の事を検討すると良いでしょう。
やらないことを決める
そもそも自分の担当範囲の仕事なのかどうかを見極める事から始めましょう。
他部署だったり、上司だったり、自分以外の人や部署がやるべき仕事であれば本来の形に戻すよう努力しましょう。
上司の期待値を調整する
高すぎる期待値を持たれていると仕事がなかなか終わりませんので、制限時間の中でベストを尽くす、そして時間は制限されている(私は忙しい、他にもやらないといけない仕事もある等)印象を相手に間接的にでも伝えましょう。
タスク管理を徹底
緊急度と重要度でタスクを割り振り、事前にタスクを整理することで、やるべきことで迷わないようにしましょう。
緊急度が高い仕事ばかりに目を奪われ、重要な仕事にも早めに着手すべきものがないか視野を広げましょう。
家族との時間の調整
家族とも仕事が忙しい時期などを予め共有し、協力してもらえる体制を作っておきましょう。
逆にプライベートを充実させる時間も組み込むように努力しましょう。
デジタルツールの徹底活用
使い回せるものは徹底的に使いまわして生産性を向上しましょう。
自分が過去に作った資料もテンプレートとして活用できそうなものを整理したり、周囲に使える資料はないか聞いたりして、ゼロから作り上げる努力を減らし、過去の資料をどう修正や活用したら良いか考える時間を増やすことがトータルの生産性を上げるでしょう。
プライベートの予定も平日に組み込んでみる
小さなところから改善に着手することで前向きになれます。
いつもなら仕事優先で考えているところを周囲に迷惑をかけない範囲からプライベートを優先にする取り組みに着手してみましょう。
平日に予定を入れてみる、というのは直接的にワークライフバランスを改善する良い取り組みになるでしょう。
まとめ:成果も時間も両立できる「投資思考」を持とう
ワークライフバランスが取れないのは、仕事とプライベートの双方を視野を広げてみて時間資産をどう分配するかという大局的な視点を持てていないということが一因として挙げられます。
自分の体力・エネルギー・時間というのは有限なので、体力回復やリフレッシュ、家族との時間も考慮して、仕事に取り掛かかれる時間が最大どれだけあるのかを客観的に見つめ直すことです。
更には本当にやらねばならない仕事に選別することで、パフォーマンスを低下させず、むしろ限られた時間でどう向上させていくかを追求する姿勢が重要になります。
また別の角度ではやらねばならない仕事に選別した後で、どう効率を上げていくかについて、過去の資料を徹底的に使い回す、活用するという考え方を紹介してきました。
直接的に有効となる取り組み、例えば平日に予定を入れてみるといったことも取り組み、気持ちを前向きにしながらワークライフバランスをうまく取っていきましょう。