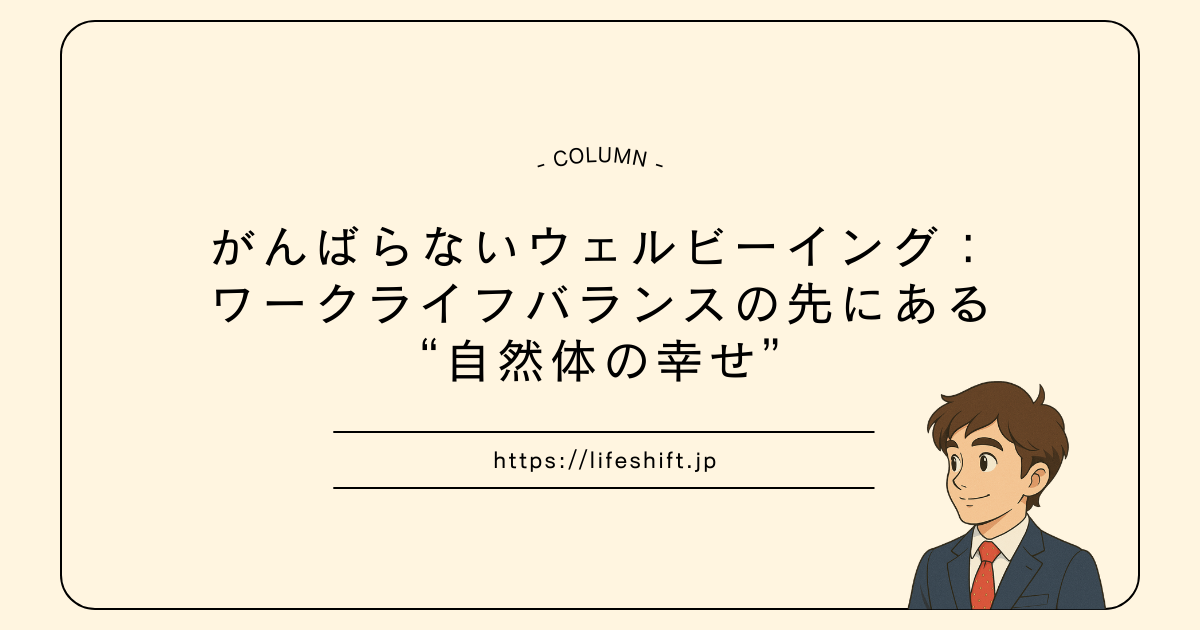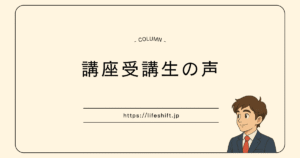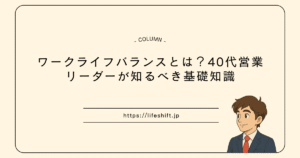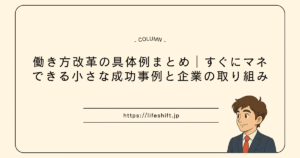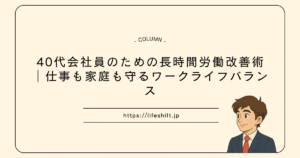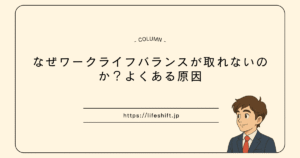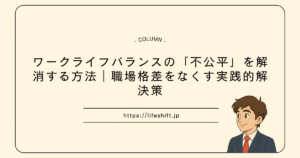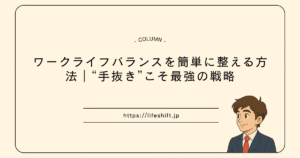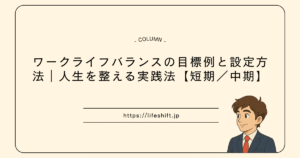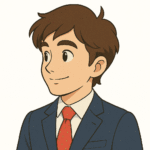
「仕事も家庭も大事にしたい」と思いながら、気づけば毎日が仕事中心になっている。 休みを取っても心が休まらない──そんな感覚を覚えたことはありませんか?
僕自身、商社で長年働いていた頃、同じような状態に陥っていました。有休を使っても結局パソコンを開き、投資や勉強で時間を埋めてしまい、「本当に休めているのか?」と疑問を感じたものです。
近年注目されるキーワードに「ワークライフバランス」と「ウェルビーイング」があります。どちらも働き方や生き方を考える上で欠かせない概念ですが、その違いが曖昧なまま使われているケースも少なくありません。
本記事では、ワークライフバランスとウェルビーイングの違いを整理しながら、僕自身の経験も交えつつ「がんばらなくても自然に幸せでいられる」生き方のヒントを紹介します。
ワークライフバランスとウェルビーイングはどう違う?
ワークライフバランスは、「仕事と生活をどのように配分し、調整するか」を指します。残業を減らす、有休を取る、在宅勤務を取り入れるなど、制度や仕組みで実現されることが多いのが特徴です。
一方でウェルビーイングは、「幸福」「健康」「生きがい」などを含む、より総合的で内面的な概念です。単に時間を確保することよりも「どれだけ心地よく、充実しているか」に焦点を当てます。
| 項目 | ワークライフバランス | ウェルビーイング |
|---|---|---|
| 意味 | 仕事と生活の時間配分を調整する考え方 | 幸福・健康・生きがいなどを含む総合的な満たされ感 |
| 焦点 | 時間・制度・外的な調整 | 心・体・社会的つながりなど内面的な質 |
| 目的 | 仕事と私生活の両立を実現する | 自然体で心地よく、持続的に幸せを感じる |
| 測り方 | 残業時間・有休取得率など数値で評価可能 | 主観的な満足度・幸福感で評価される |
| 実現方法 | 制度利用、時間管理、働き方改革 | 小さな習慣、マインドの切り替え、つながりを大切にする |
| 限界 | 時間が確保できても幸福感が伴わない場合がある | 個人差が大きく、数値化が難しい |
僕自身も、以前は「休みを取れればワークライフバランスは取れている」と思い込んでいました。しかし実際には、空いた時間に資格の勉強や投資の調査を詰め込み、心は休まらないまま。そこで初めて、「外的な調整だけでは幸福感は得られない」と気づきました。
違いを理解することは、「制度に縛られず、自分なりの幸せを描く」視点を持つきっかけになります。
ワークライフバランスが整っても幸せになれない理由
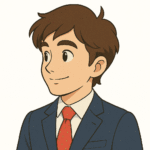
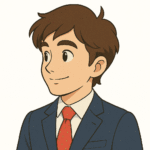
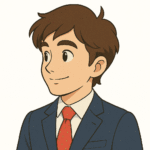
「残業が減ったのに疲れが取れない」「休みを取っても気持ちが休まらない」──そんな経験をした人も多いでしょう。
僕もかつて、制度をフル活用して休みを増やしましたが、頭の中は常に仕事や将来の不安でいっぱいでした。つまり、時間の“量”があっても幸せには直結しないことを痛感したのです。
制度や時間配分といった外的なバランスは一定の効果がありますが、それだけで幸福感が保証されるわけではありません。むしろ「もっと効率的に休まなければ」「この時間を有意義にしなければ」と考えるほど、逆にストレスを感じることもあります。
数値で測れるバランスと、体感でしかわからない幸福感のギャップ。そこに、私たちが抱えるモヤモヤの正体があるのかもしれません。
ウェルビーイングの視点から見る“がんばらない幸せ”
ウェルビーイングは「頑張って到達するもの」ではなく、日常の中で「気づき」「感じるもの」です。
僕にとってそのきっかけとなったのは、朝のランニングやブラジリアン柔術でした。大きな目標を掲げるわけではなく、身体を動かすことそのものに没頭する。気づけば気持ちが整い、自然と幸福感を感じられるようになったのです。
小さな習慣で高まる幸福感の例
- 朝の深呼吸や散歩で気分を整える
- 家族や仲間に「ありがとう」を伝える
- 趣味に没頭する時間を少しだけ確保する
成果や昇進をゴールにするのではなく、「今この瞬間を楽しむ」こと。それがウェルビーイング的な幸せであり、頑張らなくても心が満たされる状態をつくってくれます。
ワークライフバランスを土台にウェルビーイングを高める方法
とはいえ、ワークライフバランスが不要になるわけではありません。時間の枠組みや制度があってこそ、その上にウェルビーイングが成り立ちます。
僕自身、在宅勤務の制度やフレックスを「義務」ではなく「自分をサポートしてくれるツール」と考えるようになってから、気持ちがぐっと楽になりました。完璧に調整しようとせず、「今日はこれで心地いい」と思えれば十分なのです。
ウェルビーイングを高める実践例
- 会社制度を「支援ツール」として使う(リモート勤務、時短勤務など)
- 完璧なバランスを目指さず、ゆるやかな調整で心地よさを優先する
- 「足す」より「引く」発想でやらないことを決める(無駄な会議や残業)
- 家族や仲間との時間を重視する(人とのつながりは幸福感を強める)
- 小さな習慣を守る(休む、趣味を楽しむ、感謝する)
制度の枠組みに自分を合わせるのではなく、自分に合わせて制度を使いこなす。その発想の転換が、無理のないウェルビーイングにつながります。
まとめ|がんばらなくても自然に幸せになれる働き方へ
ワークライフバランスとウェルビーイングは似て非なる概念です。前者は「外的な調整」、後者は「内面的な充実」。両者を区別して理解することで、働き方や生き方に新しい視点が加わります。
僕自身、ワークライフバランスを意識するだけでは満たされませんでした。しかしウェルビーイングという考え方を知り、小さな習慣を大切にするようになってからは、「頑張らなくても幸せでいられる」感覚を持てるようになったのです。
特に40代のビジネスパーソンにとって大切なのは、「効率や成果」よりも「心の満足感」を優先してよいという安心感。自然体の幸せが、キャリアの持続性や家族との調和、そして自分自身の豊かさにつながっていくはずです。