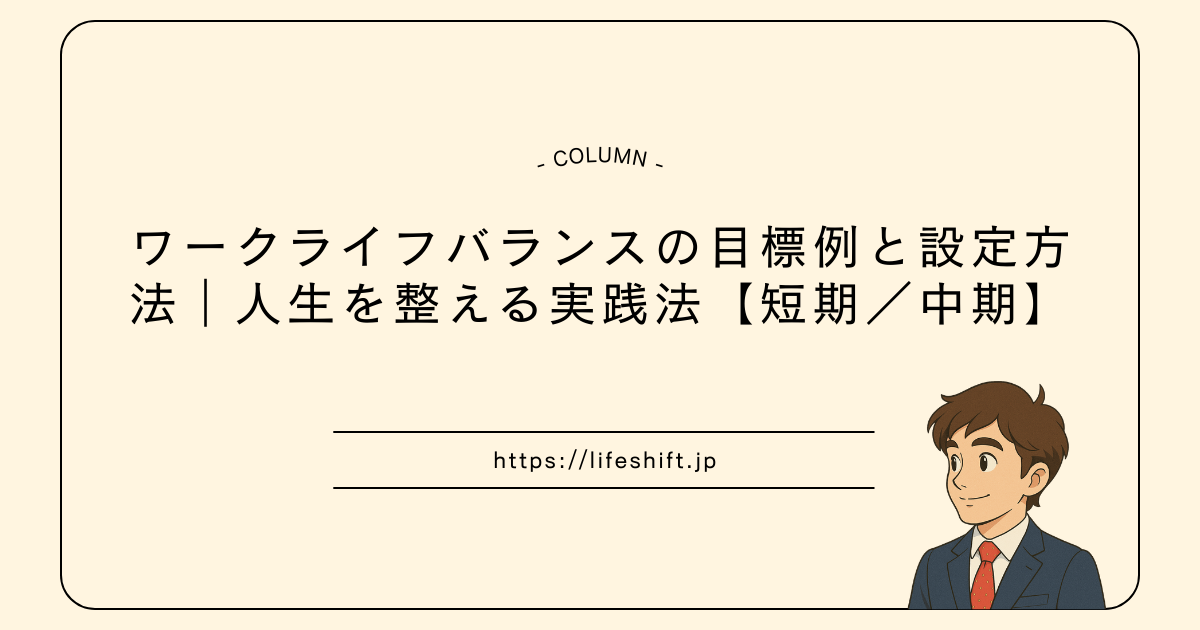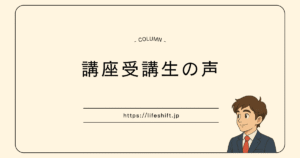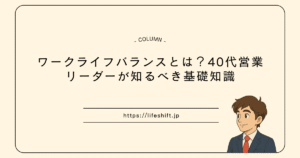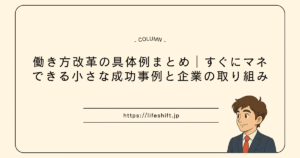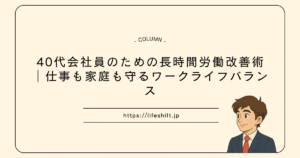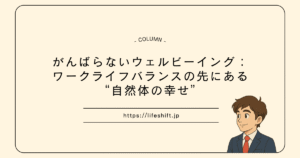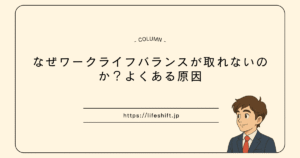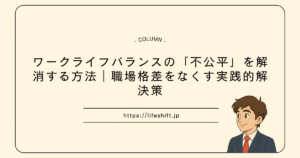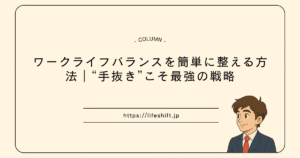「ワークライフバランスを整えたい」と思っても、実際にどんな目標を立てれば良いのか悩んでいませんか?
多くの人は、残業を減らす・定時退社を増やすといった“善意の努力”を積み上げますが、やり方を間違えると続かずに消耗します。
この記事では、まず皆さんが知りたい短期・中期の具体的な目標例を示し、そのうえで私自身の経験を交えながら、よくある落とし穴と正しい設計法、継続のコツまでを一気通貫で解説します。
ワークライフバランス目標の具体例【短期/中期で実践】
短期目標例(1〜3ヶ月でできること)
- 週に1日は必ず定時退社し、家族と夕食を共にする
- 毎朝30分はスマホを触らず、読書・軽運動・日記のいずれかに充てる
- 週2回は30分以上の有酸素運動(通勤の一駅歩き・エレベーターを階段に置換などの“足し算”でOK)
- 1日3行の日記で「今日の時間の使い方」を振り返る
- 週末は半日以上のデジタルデトックス
中期目標例(1〜3年で変えていくこと)
- 在宅勤務や時短勤務を組み合わせ、通勤時間を例えば年間100時間削減(交渉・申請・仕組み化まで含めて計画)
- 毎年、家族旅行を必ず1回実現(日程を先にブロックし、費用を毎月先取り積立)
- 副業または資格学習で将来のキャリアにつながるスキルを獲得(学習時間を週3コマ固定し、四半期ごとに成果物を出す)
- 年間10冊程度の読書+要約メモ10本作成(学びを同僚・家族へ簡単に共有して定着)
私の経験:40歳で「ワーク・インベストメント・バランス」に舵を切った理由
私は40歳前後で、「もしこのままの働き方を継続していたら、一生定年まで会社員のままだ」と痛感しました。
そこで会社を辞めても困らない資産形成を本気で進めると決め、仕事だけで手一杯の生活に更に、投資学習の時間を無理やり埋め込むことから始めました。
週2〜3日は会社を出たら即、セミナー参加や読書、学んだことの自分の資産形成への適用検討に充てました。
この期間は正直に言って楽ではありませんでした。
仕事と家庭で手一杯のところに、さらに投資の勉強を載せたからです。
それでも続けたのは決意があったからです。
結果として、投資を学ぶ過程で事業リスクへの感度が上がり、仕事の判断も速く・冴えるようになりました。
のちに、当時作った「資産形成の時間」は、家族時間や自分の余白に置き換わっていきました。
私はこのプロセスを、仕事と遊びの分離ではなく「ワーク・インベストメント・バランス」と呼んでいます。
よくある間違ったワークライフバランス目標(なぜ続かないのか)
「残業ゼロ」をゴールにしてしまう
残業を減らすことは重要ですが、それ自体は手段です。
本当のゴールは「家族と夕食をとる」「趣味に没頭する」「学び直しを進める」など、自分の価値観に直結する時間の確保です。
手段をゴール化すると、状況が変わった瞬間に崩れます。
周囲に合わせて目標を立てる
「会社が推奨しているから」「同僚もやっているから」という理由で立てた目標は、意味づけが弱く習慣化しにくいです。
必要なのは自分にとっての必然性です。
私の場合は「会社依存からの脱却」という切迫した動機が、行動の持続力になりました。
仕事とプライベートを切り離しすぎる
完全分離は現実的ではありません。
私は投資学習で磨いたリスク感覚や情報整理力を、仕事の意思決定に活かしました。
逆に、仕事で培ったプロジェクト管理の型を家庭の予定設計に応用しました。相互乗り入れがバランスを強くします。
正しいワークライフバランス目標の立て方
人生全体を「時間バランスシート」にする
キャリア・家族・健康・学び(投資含む)・趣味などの重要領域に分け、各領域の理想と現状のギャップを書き出します。
ギャップが大きい領域から、短期目標(習慣)と中期目標(仕組み)をセットで設計します。
短期=習慣化/中期=仕組み化で二段構えにする
短期目標は「週◯回」「毎日◯分」などトリガーと頻度を明確にし、チェックリスト化します。
中期目標は働き方の制度交渉、家族の年間計画、学びの四半期ロードマップなど、仕組み化に踏み込みます。
SMART+「意味」の原則で具体化する
SMART(Specific/Measurable/Achievable/Relevant/Time-bound)で目標を具体化しつつ、最後に「なぜそれをやるのか(Meaning)」を1文で添えます。
意味が強いほど、忙しいときでもぶれません。
継続させるための工夫(私が効いたと感じたこと)
小さく始め、先に時間をブロックする
私は学習を「週2〜3コマ」に分割し、カレンダーに先に予定として確保しました。
空いた時間でやる、ではなく、時間を先取りするのがコツです。
週次レビューで「時間の投資対効果」を見る
週末に3行日記を振り返り、翌週の予定に学びを反映させます。
うまくいったら強化、詰まりがあれば障害を取り除く。この微調整の継続が、やがて大きな差になります。
AI・デジタルを遠慮なく活用する
議事録要約、情報収集、定型資料作成はAIに任せ、浮いた時間を家族・健康・学びに再配分します。
ツールは目的ではなく時間を生む装置です。
なぜワークライフバランスを見直したいのか目的を考え直す
ワークライフバランスの改善に取り組んだとしても、もし表面的な取り組みであれば消耗ばかりで継続は難しいでしょう。
苦しいときでもワークライフバランスを改善したいという気持ちを手放さない為になぜ私はワークライフバランスを見直したいのか、本音を明らかにする必要があります。
以下のように深堀りして自分の気持を整理しておくことです。
- 「残業を減らしたい」→ 本当は、仕事とプライベートの両方を楽しめる時間の余裕が欲しい
- 「定時に帰れるようにしたい」→ 本当は、家族や子どもと過ごす“質の高い時間”をもっと確保したい
- 「趣味の時間を作りたい」→ 本当は、自分らしさを取り戻して心身ともにリフレッシュしたい
- 「ワークライフバランスを整えたい」→ 本当は、“仕事に追われる人生”から抜け出して、自分で人生をコントロールしたい
まとめ──“残業を減らす”ではなく“人生を楽しむ時間を増やす”へ
ワークライフバランスの目標は、単なる時間管理ではなく人生の再設計です。
私自身、40歳でワーク・インベストメント・バランスに舵を切り、最初は苦しかったですが、続けた先に家族時間と自分の余白が戻ってきました。
もし今、当時の自分と同じ悩みを抱える方が目の前にいるなら、私はこう伝えます。
「時間があったらやりたいことは何? それに向けて、少しでも毎日時間を使ってごらんよ。」
今日の15分、今週の1コマ、来月の半日。小さな投資が、未来のあなたの自由時間と安心を増やします。
FAQ(よくある質問)
Q. 忙しすぎて短期目標すら続きません。何から始めるべきですか?
A. 最小単位で始めます。たとえば「毎朝5分の読書」「週1回だけの定時退社」。カレンダーに先に入れ、終わったらチェックをつける“見える化”で自己効力感を積み上げます。
Q. 家族の理解が得られません。
A. 目標の「意味」を共有します。たとえば「家族旅行のために年間100時間の通勤を削減したい」など、具体的な便益と期限を話し合い、家族の予定表にも反映させます。
Q. 会社の制度や文化が障害です。
A. 中期目標で「仕組み化」に挑みます。会議体の曜日固定、代理アサインの設計、情報共有テンプレート整備など、チームの“時間コスト”を下げる提案から着手します。
独力での設計に限界を感じる方へ。
私が提供する「ワークライフバランス改善講座」では、あなたの価値観に基づく目標設計と習慣化を、具体的なワークとレビューで伴走します。
また、将来の選択肢を増やしたい方には「経済的独立を目指す資産形成講座」をご用意しています。学びを仕事に活かし、時間の自由度を高める「ワーク・インベストメント・バランス」を一緒に形にしていきましょう。
\あなたの働き方を見直してみませんか?/